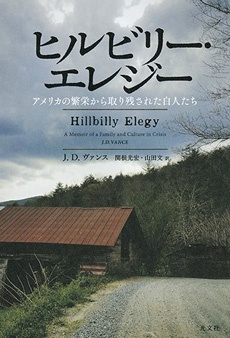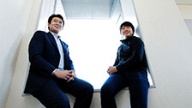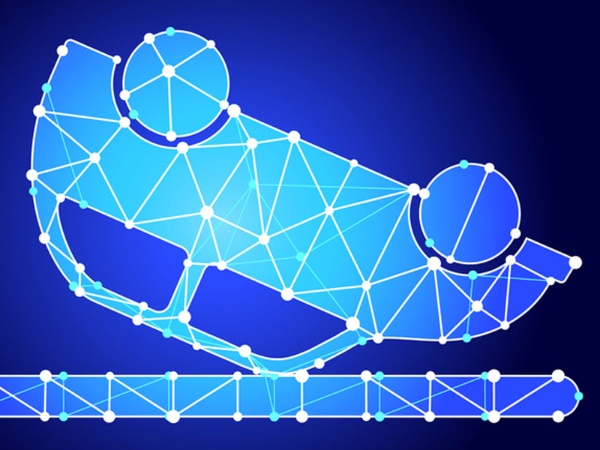20年ほど前まで、私が知っている「中国人」は、台湾人か香港人、あるいは世界各地に腰を据えた華僑だけだった。香港に住んでいた1993年から1995年ですらそうだった。中華人民共和国のパスポートを持つ中国人と知り合うようになったのは、アメリカのボストン近郊に移住した1995年以降だ。彼らの多くは、大学院で学ぶために渡米してそのままこちらで仕事を得た人たちだった。
私が住んでいるのは、家族あたりの平均年収が2000万円を超える、アメリカでも裕福な町だ。最近では、中国本土からの移民が激増している。彼らは、ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学の教授、ITやバイオ企業の管理職であり、中国系移民のコミュニティでも「成功者」とみなされている。自分自身の成功の秘訣である「教育」を重視し、わが子にも有名大学への合格を要求する。公立学校での競争を激化させる存在として、ときに、ほかの親たちから問題視される存在でもある。
初期に私がこの町で知り合った中国人は、十代のときに文化大革命(1966~76年)を経験し、その記憶が薄れないうちに渡米した人たちだ。だから、「必死に勉強して、良い大学に行って、良い職業を得る」ことを成功とみなし、それに最適な場所がアメリカだと考えている。中国人コミュニティで交流するだけの人もいるが、新しい故郷であるアメリカ社会に溶け込む努力をしている人も少なくない。
このような中国系アメリカ移民一世ではなく、チャイナタウンに住む華僑でもない中国人を私が初めて見かけたのは、2004年に家族旅行をしたフランスでのことだった。
ベルサイユ宮殿内の見学は一方通行の順路で、順番を待つ人の長蛇の列がある。それなのに、逆戻りして多くの人に迷惑をかけている団体がいた。フランス人が眉をひそめて「ウララ!」と睨んでいるのは、どうやら中国からの観光客のようだ。駐車場には中国語がついた大型バスも並んでいた。
それを見て、私は1984年に一人で歩き回ったパリのことを思い出した。オフシーズンのノートルダム寺院で、ヴィクトル・ユーゴーの小説を想像しながらゆっくり寛いでいたところ、ガヤガヤうるさい団体がなだれ込んできた。それまで静かに見学していたフランス人たちは、「ウララ!」と憤慨したように寺院を出ていってしまった。彼らが「ジャポネよ」と呆れたように囁き交わしたのは、日本人の団体観光客だった。
第二次世界大戦後の高度成長期を終え、バブル景気を迎えようとしていた時期の日本では、庶民でも簡単に外国旅行ができるようになっていた。それと同じように、中国の庶民も外国旅行ができるようになったということなのだ。中国の変化を、このとき実感した。
それから13年の間に、中国はさらに変わった。
以前は日本で留学生招致の説明会を行っていた某アイビーリーグ大学は、あまり留学生が来ない日本での説明会をやめ、中国で2カ所行うようになった。
中国からの留学生が増えただけではない。彼らは驚くほどリッチになった。
娘のボーイフレンドの大学時代のルームメイトは、寮のベッドに何万円もするサテンのシーツを使い、週末にはニューヨークまで行って何十万円もの買い物をしたという。「何百ドルもする名前も知らないような保湿ローションを10本くらい一度に買い込むんだよ!そんなアメリカ人の男子学生には会ったことがない」とよく話題になっていた。
むろん留学生全員がそうではないが、リッチな中国人留学生の驚くような逸話はあちこちから聞こえてくる。どうやら、最近お金ができた親たちが、ひとりっ子にすべてを費やしているようなのだ。
1980年代後半に住んでいた表参道にある三宅一生のショップを、昨年久々に訪れたところ、表参道全体が賑わっていて驚いた。話を聞くと、「中国からのお客様なんです」と言う。そこで知ったのが中国人観光客による「爆買い」という現象だった。これも、1980年代のパリでの日本人観光客を連想させる。
主力であっても主役になれない農民工
しかし、これらが現在の中国人の一般的な姿かというとそうではないようだ。
私たちがたぶん一生知り合うこともないが、中国を理解するために重要な人々がいる。それは、中国に3億人いるといわれる「農民工」だ。
1988年に留学して以来、香港や中国で仕事を続け、地元で交友関係を築いてきたノンフィクションライターの山田泰司氏は、彼らのことを「中国の主力でありながら、絶対に主役にはなれない人たち」と呼ぶ。
私も、山田泰司著の『3億人の中国農民工 食いつめものブルース』を読むまで、農民工と呼ばれる人々のことはまったく知らなかった。収入格差があることは想像の範囲だったが、21世紀のいま、底辺の人々がこれほど凄まじい生活をしているというのは衝撃的だった。
農民工は、農村からの出稼ぎ労働者のことである。
山田氏はそれが誕生した経緯をこう説明する。
「毛沢東主席の時代、すなわち新中国が成立した1949年から文化大革命が終了する1977年ごろまで、中国では、農民が都市へ移動することを厳しく制限していた。社会主義体制の下、国民に配給する十分な食糧を確保する必要があったことが大きい。
それが、文化大革命が終わり最高実力者の地位に就いた鄧小平氏が打ち出した改革開放政策により、都市部の開発や工業の推進を決めると、それに伴い製造業や建築業で労働力が必要になった。ここで、農民は自宅のある農村を出て都市へ出稼ぎに行くことを許された。農民工の誕生である。」
出稼ぎ先の都市部で医療や教育などの社会福祉を受けることができないのに都会に行く農民がいるのは、農業で「食いつめる」からだ。農業の年収はなんと3万2000円だという。むろん、自分で作る農作物を食べる以外は何もできない。
日本がバブル景気の頂点にあった1990年、中国の人口のなんと73.5%が農民だったという。その後の都市開発で、多くの農民が「農民工」として都市部に移動して労働力になった。
農民工の子どもたちは都市部で教育を受ける権利がないので、「留守児童」として故郷に残される。農民工の年収は、農民よりましだが、働いても、働いても、月給は6万円とか7万円止まりだ。それなのに、都市開発で家賃だけは倍増していく。景気が停滞すると、彼らが真っ先に職を失う。
それにしても、農民工の暮らしは壮絶だ。部屋の中にトイレがそのまま設置されているアパートやロウソクの味がするパンの話を読んでいるうちに、気持ちがどんどん沈んできた。私がこれを一生続けなければならないとしたら、生きていく希望など持てない。
悲観的なヒルビリー、夢を持つ農民工
これは、アメリカでベストセラーになった『ヒルビリー・エレジー』を読んだときの感覚とも似ている。
ドナルド・トランプの強い支持基盤として知られるようになった「ヒルビリー」とは田舎者の蔑称だ。『ヒルビリー・エレジー』の著者J. D. ヴァンスはこう説明する。
「先祖は南部の奴隷経済時代に日雇い労働者として働き、その後はシェアクロッパー(物納小作人)、続いて炭鉱労働者になった。近年では、機械工や工事労働者として生計を立てている。……つまり、彼らは『アメリカの繁栄から取り残された白人』なのだ」
「繁栄に取り残された労働者階級」という意味で、中国の「農民工」は、「ヒルビリー」と似たところがある。どちらも、貧困が代々伝わる伝統になってしまい、なかなかそこから抜け出せない。
しかし、異なる部分も多くある。
ヒルビリーは「アメリカで最も悲観的な人々」だ。人種差別の対象になっている黒人やヒスパニックでさえ、過半数は「自分の子どもは自分より経済的に成功する」と次世代に期待している。だが、ヒルビリーの過半数は、子どもの世代のほうが自分の世代より悪くなると思っている。
それに比較して、中国の農民工は「明日には自分の番が回ってくる」という夢を捨てていないようなのだ。アメリカのヒルビリーは政府から多くの援助を受けているが、中国の農民工は国から保護など受けていない。それでも、彼らは、怒りもせずに、明日のほうが良くなると信じて黙々と働く。
もうひとつの違いは、ロウソクの味がするパンしか食べられない貧しい農民工たちの心の豊かさだ。外国人である山田氏と友情を築いた彼らは、自分が食べていくことさえ困難なのに、必ず「ご飯を食べに来て」と招待する。そこに、ホロリとした。絶望や憤りを移民や外国人に向けるヒルビリーとは、大きく異なる。
この本を読んでいるときに改めて実感したのが「中流階級」の重要性だ。
1970年代、日本では「一億総中流」という表現があった。人口約1億人の日本人のほとんどが、自分のことを「中流」とみなしていたのだ。この時期の日本人は、今ほど物を持っていなかったが、自分の暮らしに満足し、将来に夢を持っていた。
だが、最近の日本のソーシャルメディアでは、「親の時代はラッキーだった」、「親の世代より、子の世代のほうが悪くなる」といった悲観的な意見が目立つ。
中国においても、農民工の楽観性や忍耐がそろそろ尽きようとしているようだ。
どの国でも、国民の多数が「将来が良くなる」という夢や楽観性を失うと、「政府は何もしてくれない。すべてを壊してしまえ」という極論に惹かれるようになる。それがアメリカの「トランプ現象」でもあった。
現状を打ち壊すのは、一時的にはすっとするかもしれないが、国が不安定になって、状況は以前より悪化する。その悪影響を真っ先に受けるのが、低収入の労働者階級だ。
個人的に恵まれた環境にある人は、「自分には関係がないこと」と思うかもしれない。だが、中流階級が消えることによって、国は不安定になる。そうなったときに影響を受けるのは国民全体だ。
また、収入格差がアメリカより激しい中国で社会が不安定になったら、隣国も影響を受ける。
アメリカと中国という二つの大国で起きていることは、日本にとっても無視できないことなのだ。

エッセイスト、洋書レビュアー、翻訳家。助産師、日本語学校のコーディネーター、外資系企業のプロダクトマネージャーなどを経て、 1995年よりアメリカに移住。2001年に小説『ノーティアーズ』で小説新潮長篇新人賞受賞。翌年『神たちの誤算』(共に新潮社刊)を発表。他の著書に『ゆるく、自由に、そして有意義に』(朝日出版社)、 『ジャンル別 洋書ベスト500』(コスモピア)、『どうせなら、楽しく生きよう』(飛鳥新社)、『暴言王トランプがハイジャックした大統領選、やじうま観戦記』(ピースオブケイク/Kindle版)、『トランプがはじめた21世紀の南北戦争: アメリカ大統領選2016』(晶文社)など。翻訳には、糸井重里氏監修の『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』(日経BP社)、『毒見師イレーナ』(ハーパーコリンズ)など。
登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。
※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。