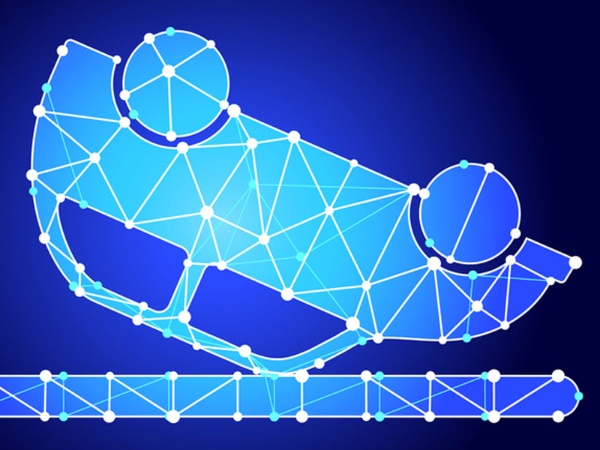「ドーハの悲劇」

今年6月13日、イランの首都テヘランで開催されたサッカー男子ワールドカップ・アジア最終予選、日本代表はイラクと引き分けた。
そう言えば、24年前の1993年10月。日本代表は、後半ロスタイムで失点、イラクと引き分け、94年ワールドカップ米国大会への出場権を失った。「ドーハの悲劇」である。あの時も、対イラク戦はカタールの首都、ドーハで開催された。
そのカタール・ドーハが、今、大変なことになっている。
2022年のサッカーワールドカップのカタール開催も危ぶまれる事態である。
4カ国の対カタール断交
6月5日、エジプト、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーンの中東4カ国(注)は、カタールがムスリム同胞団や「イスラム国(IS)」、アルカイダ等のテロ組織・過激主義者を支援し、各国の内政に干渉しているとして、突如、国交断絶を通告した。同時に陸路・海路・空路という国境をすべて封鎖、カタール機・船舶の領空・領海の航行禁止、外交団の48時間以内の退去、カタール国民の2週間以内の退去など、事実上の経済封鎖を命じた。

この措置により、物資の多くをサウジ国境からの陸上輸送とUAEのドバイからの海上輸送に依存しているカタールでは、一時的に、スーパーから食料品や生活必需品が売り切れるなど、混乱が発生した。トルコやイランからの緊急空輸などが行われていること、そして国自体が裕福であることから、コストをかければ物資の調達に困るような事態にはならないと思われるが、少なくとも国内物価の上昇は避けられないであろう。
また、現在、カタールでは、2022年のサッカーワールドカップに向けた施設の建設工事が急ピッチで進んでいるが、資材の多くをサウジから陸路で運び込まなければならない。サウジ系・UAE系の工事業者も多いことから、今後の作業の進捗が危ぶまれている。
天然資源で潤うカタール
アラビア半島はサウジアラビア(日本の約6倍の面積)がその大部分を占めるが、カタールは、その中央部のアラビア(ペルシャ)湾に突き出した半島部分にある首長国(秋田県よりやや小さい面積)である。人口は約240万人で、うち自国民は約10%にとどまる。それ以外は外国人労働者である。豊富な石油・天然ガス収入を背景に、積極的な国家建設、国民への高福祉を進めた、典型的な「レント(地代・剰余価値)国家」である。
第一次世界大戦後、英国の保護領となり、英国のスエズ以東撤退に伴い、1971年に独立した。首長は、サウジ中央部のネジド地方から19世紀に移住した豪族サーニ家が、宮廷クーデターなどはあったものの、世襲している。
先代のハマド首長が宮廷クーデターで首長に就任した1995年以降、カタールは、全方位型の独自外交を展開している。同時に国内の自由化、民主化を推し進め、2004年6月には、憲法に相当する「恒久基本法」を制定し、サーニ家の統治を前提に、三権分立の政治体制と女性参政権を認めた。
全方位型の独自外交
カタール独自の積極外交として注目されるのは、1995年、アル・ウデイドにサウジから撤退した米空軍基地を受け入れるとともに、米海兵隊旅団規模の装備の事前集積を行うなど、米国の中東最大の軍事拠点を提供したことである。
また、96年には、衛星放送「アルジャジーラ」を開局し、中東系の通信社としては自由主義・民主主義的色彩の濃い世界的なメディアを立ち上げた。アルジャジーラは、スポンサーであるカタール政府は別として、周辺諸国の政府批判を繰り返すなど、周辺諸国からは何度も閉鎖要求が出ている。
さらに、2009年のガザ侵攻により閉鎖されたものの、1996年からはアラブ圏では唯一のイスラエル通商代表部を設置していた。
並行して、中東域内のみならず、世界規模の国際会議やスポーツイベントを積極的に誘致し、カタールの発信に務めた。例えば、2001年11月の国際貿易機関(WTO)第4回閣僚会議(ドーハ・ラウンド)、2012年12月の気候変動枠組み条約第18回締約国会議(COP18)などの国際会議。それに2006年のアジア大会、2019年開催予定の世界陸上競技大会、そして2022年開催予定のサッカーワールドカップなどと、国際的なスポーツ大会の開催国としても存在感を示してきた。
同時に、従来から、エジプトの「ムスリム同胞団」、パレスチナの「ハマース」、レバノンの「ヒズボラ」等の組織に対しても、アラブの「抵抗運動」であるとして、資金援助や連絡拠点の提供などを行っていると言われてきた。「テロリスト」、「過激派組織」の定義が、関係各国・関係者の間で異なる中では、こうしたカタールの支援が周辺各国の緊張を高めているとの批判も多い。また、こうした行為は、カタールにとっての「保険金」、あるいは、ヤクザに対する「みかじめ料」に近いとする見方もある。
今回の断交の背景には、こうした事情も大きく影響している。
ガス大国としてのカタール
カタールは、OPEC(石油輸出国機構)加盟国ではあるものの、産油国としては大きい方ではない。2016年の原油生産量は68万BD(=Barrels per Day、1日当たりの原油生産量)と14カ国中10番目である。だが、わが国の原油輸入先としては、約30万BDと9%を占める。サウジ、UAEに次ぐ第3位となっている。
むしろ、カタールは、産ガス国としての存在感が大きい。天然ガスの埋蔵量の約15%を占め、ロシア、イランに次ぐ第3位のガス埋蔵国である。液化天然ガス(LNG)の輸出能力は年間約8000万トンと、世界最大の輸出国で、わが国の輸入先として、豪州、インドネシアに次ぐ第3位、約15%を占めている。2011年の東日本大震災の後、原子力発電所の運転停止に伴い、LNG火力発電所の稼働増強のため、カタール産のLNG輸入を増量したことは記憶に新しい。
カタールは、今回の断交国エジプトにもLNGを輸出しており、UAEにはガス状の天然ガスを「ドルフィン・パイプライン」で供給しており、UAEの天然ガス需要の約30%を賄っている。さらに、このパイプラインは、オマーンに繋がっており、オマーンにも天然ガスが供給されている。現時点においては、このパイプラインは引き続き従来通り稼働している。
カタールの北方海上に広がるガス田「ノース・フィールド」は世界最大の構造的ガス田と言われ、豊富な埋蔵量を誇っているが、イラン領海から広がる「サウス・パルス」ガス田と地質構造的に繋がっていると見られることから、カタールは、伝統的にイランに配慮した、宥和的な外交政策を取っている。
また、天然ガスについては、ロシア、イラン、カタールの3カ国が中心となって、「ガス輸出国フォーラム」(GECF)を組織し、毎年閣僚会議を開催するなど、交流・情報交換が行われており、将来的には、「ガス版OPEC」の形成を目指す動きも見られた。
現時点では、断交当事国向けを含め、石油、天然ガスの輸出には、直接的な障害は出ていない模様であるが、サウジ、UAEでは、多港積みタンカーの場合、前港・次港をカタールとする寄港を拒否している模様であり、積み地の変更を必要とするタンカーも出るものと思われる。また、大型タンカーの補給地であるUAEのフジャイラでは、カタールに寄港するタンカーへの補給を拒否している模様である。
断交の直接的契機
前述した通り、6月5日に突如、国交断絶という強硬な措置が取られたわけであるが、以前から、サウジとカタールの間には対立の兆しはあった。
5月21日、サウジは、トランプ米大統領の初外遊に合わせ、首都リヤドに、カタールのタミーム首長を含む、55カ国首脳を集め、米・アラブ・イスラム首脳会議を開催、テロリスト・過激派組織の打倒とイランとの対立姿勢を確認した。
ところが、23日、タミーム首長が国内の軍事式典で、・周辺諸国は、過激派組織を支援している、・ムスリム同胞団やハマースは、抵抗組織であり、テロ組織ではない、・イランと敵対することは賢明ではない、と発言したと、周辺各国メディアが、カタール通信をキャリーする形で一斉に報じた。
これに対し、カタールメディアは、放送のハッキングによる「フェイク・ニュース」であるとして、「発言」を否定した。結局、真相はやぶの中である。クウェートがこの対立の仲裁に入り、妥協案を示したと言われているが、その後、何らかの事情でこじれ、6月5日の断交に至ったのではないか、と見られる。
大使召還とリヤド合意
ただ、周辺各国にとって、カタールとの対立は、今に始まった話ではない。
従来から、カタールは、ムスリム同胞団を積極的に支援してきたが、これを警戒する周辺諸国やエジプトは、いら立ちを募らせ、2014年3月には、サウジ、UAE、バーレーンがカタール駐在大使を引き揚げ、外交関係を格下げする事態が発生していた。
ムスリム同胞団は、1928年にエジプトで始まったイスラム法によるイスラム国家の確立を目指す政治運動であるが、その特徴として、医療や教育といった大衆向けの社会活動を基盤としている。
エジプトでは、2011年2月の「アラブの春」で、約30年続いたムバラク独裁政権が退陣したあと、ムスリム同胞団を中心としたムルシ政権が成立したが、その復古的政策から、民心が離れ、13年7月には軍事クーデターにより、現在のシーシ政権が成立した。ムスリム同胞団は、シーシ政権から見ればテロリスト・過激派組織であり、湾岸君主制諸国にとっても、ムスリム同胞団の草の根的色彩は脅威である。
この時は、クウェートのサバ―ハ首長の精力的シャトル外交により、14年11月、カタールはムスリム同胞団と決別する旨の「リヤド合意」により和解し、正常な外交関係を回復した。
「防波堤」としてのGCC
さらに、サウジにとって、気になることは、カタールのイランに対する宥和的姿勢であろう。
アラブ民族の盟主・イスラム教の盟主を自任するサウジにとって、歴史あるペルシャ民族とイスラム教の少数派シーア派を代表するイランは、中東における地域大国として、ライバル関係にある。OPECの価格政策をめぐっても、サウジは穏健派の代表として、イランは強硬派の代表として、対立することが多かった。
1979年、労働者・学生等によって王政が打倒された後、亡命中のホメイニ師の帰国によって、シーア派の政教一致国家となったイランに対して、サウジ、UAE、クウェート、バーレーン、カタール、オマーンの湾岸君主制国家6カ国は、シーア派宗教革命の輸出を阻止するため、81年5月、湾岸協力会議(GCC)を結成、協力体制を強化することとした。
これら6か国の君主一族はイスラム教の多数派であるスンニー派であるが、アラビア(ペルシャ)湾周辺はイランに近いこともありシーア派住民も多い。バーレーンにおいてはシーア派住民が多数派であり、サウジでも油田地帯である東部湾岸にはシーア派住民が多い。そのため、ペルシャ湾は「シーア派の海」とも言われている。
その後、GCCは、1990~91年の湾岸危機・戦争に当たってクウェートを軍事的に支援、2011年3月の「アラブの春」ではバーレーンのシーア派民衆暴動に介入、2015年3月にはイエメン空爆を行うなど、軍事・治安面での協力を進めた。さらに、石油収入の低迷を背景として、GCC統一付加価値税の導入が決定され、統一関税制度の導入や通貨統合も検討されるなど、欧州共同体的な経済統合を目指す方向も打ち出されている。
イランのサウジ包囲網
特に、米国による「イラク民主化」の結果としてのイラクのシーア派国家化と国内分裂、イラン・イラク同盟関係の成立、さらには、イエメンのシーア派クーデターを含めて、イランによるレバノン・シリア・イラク・イランを結ぶシーア派のサウジ包囲網が形成されつつある現状においては、サウジにとっては、GCC強化を通じたイラン対策強化が、安全保障上の最優先課題であろう。
そうした中で、隣国カタールが、独自路線で勝手なことをしては困る。それがサウジの本音だろう。
トランプ大統領のリヤド訪問直後には、バグダッドで、カタールの外相とイランの革命防衛隊司令官が会談したと伝えられている。
サウジとしては、核合意を締結し経済制裁を解除するなど、親イラン的なオバマ政権から、イランを敵視するトランプ政権に交代したことは、懸案を解消するきっかけになったはずだ。トランプ大統領の初外遊によって、オバマ時代に悪化していたエジプトなどを含めた伝統的友好国との関係が修復されるとともに、イラン封じ込めが国際的に確認された直後のタイミングを見計らって、エジプトやUAEといった友好国とともに、カタールに対して政策変更を強要したということであろう。
今後の展開
断交後、2週間が経過し、断交国からのカタール国民の退去期限も経過した。引き続き、クウェートを中心に双方の仲裁が行われているが、出口は見えない。
当初、5月23日のタミーム首長の「発言」を「フェイク・ニュース」であるとして、各国の理解を求めようとしていたカタール側も、サーニ家一族のムハンマド外相が、「誰にも、降伏はしない」、「経済封鎖を解除しない限り、交渉には応じられない」として、対決姿勢を強めている。
財政的には豊かなカタールゆえ、短期的には経済的に耐えられなくなることはないことから、問題解決までには長期間を要することになろう。
それにしても、米国も困ったものである。
トランプ大統領は、カタール断交について、カタールはテロ支援国家であると非難し、サウジなどを支持している。一方で、国防総省や国務省は、サウジなどに冷静な行動を促し、事態の鎮静化を目指すという、ちぐはぐな対応になっている。トランプ大統領が、サウジに置いておけなくなった空軍基地がカタールにあることを認識していたか疑問視する見方さえある。
どう見ても、カタールは米国の対イラン政策変更の犠牲者である。
今回の国交断絶は、中東におけるサウジ対イランという対立軸が明確になる中で、双方に挟まれた小国が独自路線で生き抜いてゆくことが、いかに難しいかを示している。独自外交を追求するためには、外交環境の変化というリスクを十分に考慮しておかなくてはならない。保険の掛け過ぎは、かえって危険なのかもしれない。
同時に、こうした小国の独自外交が、大国間のバランスを崩してしまいかねないことも認識しておく必要があろう。カタールのムハンマド外相は、ロシアにも飛び、ラブロフ外相に理解を求めた。ロシア・イラン・カタールは天然ガスの三大埋蔵国でもある。
原油価格への影響
さて、今回も、原油価格はほとんど反応しなかった。
6月5日のニューヨークWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)先物価格は前日比0.26ドル安の47.60ドルと下落した。
直後の6月7日にはイランのテヘランで「イスラム国(IS)」による国会議事堂とホメイニ廟の連続爆破、18日にはイランによるISに対する弾道ミサイルの報復攻撃、さらには、19日にはサウジによるイラン革命防衛隊船舶の拿捕事件も報道された。
このように中東情勢が緊迫度を高めているのに、WTI先物は10カ月ぶりの安値を記録した。OPECと非OPECの協調減産合意前の水準に逆戻りしたことになる。地政学リスクの高まりの中での原油価格低迷をどう理解するか。
市場は、本当に、こうした対立をOPEC内での結束を弱めるものとして、供給過剰に拍車をかけるものと理解しているのであろうか。
筆者には、サウジとイランの対立軸は、「時限爆弾」、あるいは「地雷」のようなものに思えてならない。その回避に向けた努力を行うとともに、危機管理を考えておいた方が良いと考える。
ここまで書き上げて、カタールに対する具体的な要求リストを作成中といわれるサウジから、6月21日、皇太子交代という大ニュースが飛び込んできた。このニュース自体は、前々から噂されていたことであり、驚きはしないが、なぜこのタイミングなのか、が気にかかる。そして、副皇太子から昇格したムハンマド・ビン・スルタン新皇太子が、対イラン強硬派と見られ、今回の断交措置をリードしたと言われるだけに、この対立がエスカレートしないか、懸念されるところである。
(次回に続きます)
登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。
※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。