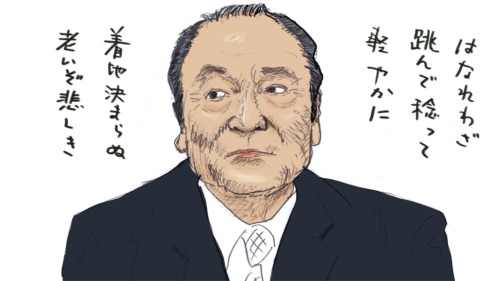
スポーツの競技団体に関連したパワハラが次々と告発されている。
昨年の後半、日本相撲協会内部での暴力事件が暴露されて以来続いている動きだ。
あの時、相撲協会内部の権力争いと「かわいがり」を題材に制作された告発と嗜虐の一大電波叙事詩は、膨大な放送時間とのべ視聴者数を獲得するに至った。その結果、パワハラ告発と暴力追放を錦の御旗に押しまくる人民裁判放送企画は、半年のロングランを可能ならしめる黄金のコンテンツであるということが証明されたわけで、このことが、現在の告発万能の流れを決定づけている。
恒常的に尺の稼げる話題を求め続けている放送現場のコンテンツハンターは、次なるパワハラの噂を求めて、取材……に走り回りたいところなのだが、そんな予算も当面ありゃしないので、とりあえず週刊誌を開いて翌日放送分のネタを探す。その結果、この半年ほど、アメフト、ボクシング、体操の世界を舞台としたパワハラ告発連続企画がそれぞれ2カ月ほどずつ上演され、それぞれに好評を博している次第だ。
で、ここへきて新たにウェイトリフティングと駅伝の組織の中でのパワハラがメニューに加わろうとしている。
私たちは、どうしてこれほどまでにパワハラが好きなのだろうか。
スルガ銀行の不正融資関連のニュースにも、最近「パワハラ」という面から新しい光が当てられている。
もしかしたらこの事件は、この先、融資の適正さや資金の流れとは別に、組織的なパワハラを告発する案件として注目を集めることになるのかもしれない。
融資そのものはスポーツ競技ではない。
しかしながら、苛烈なノルマと競争が介在している点では、過当競争に苦しむ金融機関の社員と五輪競技やプロスポーツ予備軍の選手たちが置かれている立場はそんなに遠いものではないわけで、してみると、スルガ銀行内部で繰り広げられていたとされる猛烈なパワハラは、あれはあれで昨年来話題になっている、一連の競技団体内部のパワハラと選ぶところのないものであるのかもしれない。
今回は、うちの国のパワハラの現状について考えてみることにする。
この一年ほど、明るい時間帯のテレビは、毎日のように誰かのパワハラを告発している。
やれどこそこの誰それがほかの誰かに暴言を浴びせたとか圧力をかけたとかいった調子のおよそかわりばえのしないお話を、それこそ微に入り細を穿つ形で再現してみせているそれらの番組企画を眺めながら、私はいつも釈然としない気持ちに襲われる。
パワハラを発動した人間がテレビ画面の中で指弾されるのは、なりゆきからしてしかたのないことなのだろうとは思う。
でも、そうは言っても、この種の問題は、特定個人の罪状をあげつらって、その人物の人間性をよってたかって非難すればそれで済むというタイプのお話ではないはずだ。
たとえば、パワハラの背景にある日本人の集団性にスポットを当てるとかして分析を深めないと、この話題は先に進まない……などと思うのは、しかしどうせ素人考えというヤツなのであろう。
テレビの中の人たちにしてみれば、彼らの目的は先に進むことではない。
謎を解明することでもない。
彼らはたぶん、喜怒哀楽のうちのどの部分であれ視聴者の感情を揺さぶることができれば勝ちだ、というふうに考えている。まあ、置かれている場所からして当然の咲き方だ。そこのところを責めようとは思わない。好きに咲けば良い。
むしろ注目しなければならないのは、作り手の側の意図よりも、受け手であるわれわれの側の心理だ。
つまり、昨年来、ほとんどまったく同じエピソードの繰り返しにしか見えない各方面のパワハラ事案が、あとからあとから発覚してはニュース原稿に仕立てあげられ、テレビ裁判にかけられた上で電波仕置人たちの処刑放送に供されているのは、この種の近代リンチコンテンツが、堅実な視聴率を稼ぐことが広く関係者の間で周知されているからだということだ。
要するに、わたくしどもこのちっぽけな島国に暮らす小市民は、威張っているオッサンを寄ってたかって十字架にかけて晒すタイプの見世物が大好きなのだ。あらためて自分の胸に手を当ててみると、実に恥ずかしい話ではあるが、実際に大好きなのだから仕方がない。
ただ、なんとなくのんべんだらりと視聴してしまっている昼下がりのテレビの視聴者の一人として自己弁護すれば、昨年来引き続いているパワハラ告発企画のワイドショー独占化傾向は、必ずしもそれがわれわれの嗜虐欲求を刺激するからという理由だけで引き起こされている事態ではない。
たしかに、威張っているオヤジをみんなしてよってたかってヘコませるのは面白いし痛快でもある。
が、私たちが真っ昼間のバカなテレビに誘引されている理由はそれだけではない。
視聴者の少なくとも一部は、画面の中で延々と描写されるうちの国の閉鎖組織にありがちなどうにも陰湿かつ愚かなパワハラの様相を眺めながら、相応の反省もしている。
このことは、ぜひ大きめの声でお伝えしておきたい。
私自身、昼の時間帯の情報番組がこの約1年間(横綱日馬富士の暴行事件は去年の10月ですよ)繰り返し放送し続けていたパワハラ告発企画を、自分でも意外なほど長い時間視聴してしまったのだが、その理由は、もちろん面白かったからではない。
楽しかったからでも勉強になると思ったからでもない。
視聴実感としてはただただ不愉快だった。
にもかかわらず、ザッピング途中にふと目を留めたそれらの画面から、すぐにチャンネルを変えられなかったのは、思い当たる場面が多すぎて、こっちのアタマの中が動き出すことを止められなかったからだ。
これはとても大切なポイントだ。
テレビで放映されるある種のコンテンツは、その完成度によってではなく、その粗雑さによって、視聴者の脳内を撹拌するのだ。
テレビの番組の中には、ときに、制作物として優れているがゆえに視聴者を没入させるタイプのコンテンツが含まれている。
丹念に取材されたドキュメンタリーや、美しい画面をふんだんに提供してくれる自然番組や、脚本と演出の秀逸なドラマなどがそれに当たる。そういう番組に出会う機会は幸運だし、それらの番組がもたらしてくれる時間は真に貴重だ。
ただ、テレビが提供してくれる面白さの大きな部分は、番組としての完成度とは別のところにある。
たとえば、ハプニングとしての意外性や、画面の中に偶然映り込んでいる景色の突拍子のなさが、視聴者の目を釘付けにすることは珍しくないし、ほかにも、画面の中でやりとりされている対話の稚拙さや品の無さのようなものが、こちらの関心をひきつけるケースもある。
パワハラ告発コンテンツがわれわれの興味をひいてやまないのは、そこで紹介されているひとつひとつの挿話や事例が、わたくしども日本の常民良民にとって、あまりにも思い当たるフシのある実体験だからだ。
「ああ、いるよね、こういうヒト」
「オレが30代の頃に半年だけ働いたブラック企業の課長がまさにこいつとおんなじしゃべり方をするオッサンだった」
「なんというのか、この恫喝の仕方、身に覚えしかないんだが」
「夫婦でパワハラの最強ヒメヒコの一対って珍しくないと思う」
「1人のジャイアンに5人のスネ夫がかしずいている構図もオレの経験とぴったり一致してるな」
「っていうか、強いチームのコーチってほとんど全員こういう感じのヒトだぞ」
「普段から怒鳴ってる人間の声帯から出てる声って、最初の第一声でこっちに伝わるからな」
「そうそう。パワハラジジイの声って、音量が小さくても独特の強制力がある」
「なにしろ30年間で2000人ぐらいを怒鳴り倒してきた実績が作った声のサビだからな」
「正直な話、オレはあの声で命令されたら、どんな命令であっても服従すると思う」
と、たとえば日本ボクシング連盟の山根明会長の語り口や、日大の事件に関連して画面に召喚された一連の登場人物の立ち居振る舞いを眺めていると、人々は、いやでも自分がこれまでの人生の中で遭遇した幾人かの暴君の顔を思い出す。
誰であれ、この国の組織の中で権力が振るわれている現場に出くわした経験を持っている人間であれば、パワハラについては一家言を持っている。
その誰もが持っている一家言が、このコンテンツの人気を支えている。
パワハラについては、誰もが内心に傷と痛みとうしろめたさを伴う複雑な感情を持っている。だからこそ、他人のパワハラであっても、われわれはその現場から容易に目を離すことができないのだ。
ながらく少年野球のコーチをやっているN塚という友人が、つい半月ほど前にポツリと言っていたことだが、子供たちに野球を教える監督やコーチの中には、勘違いをする人間が少なからずいるのだそうだ。
「勘違いって、どういう意味だ?」
「自分の教えが正しいって思い込むんだよ」
「ん? 正しいと思うから教えてるんじゃないのか?」
「それが逆なんだな。子供っていうのは、どんなことを教えても、必ず言った通りにやる。びっくりするほど素直なんだよ」
「で?」
「だからそれで大人の方が勘違いするわけだよ」
「子供が従ってるんなら、指導者としては成功してるんじゃないのか?」
「いや、順序が逆なんだよ。正しいから子供たちが言いなりになるんじゃなくて、子供たちが自分の言いなりになるから、自分が正しいと思い込む。それで変な自信をつけちゃう人たちがたくさんいる」
「それがいけないのか?」
「最悪だよ」
「どう最悪なんだ?」
「うーん、うまく説明できないけど。適当なことを偉そうに教えてる指導者が現場にはヤマほどいるってことだよ」
彼の言っていることの核心の部分がどういうことなのかはともかく、子供を相手に何かを教える立場の人間が、子供たちが自分の「言いなりになる」ということに嗜癖して行く感じは、なんとなくわかる。
私自身は、他人の子供に何かを教えた経験は持っていないのだが、あるタイプの教えることの好きな人たちが、教える内容そのものよりも、「言うことを聞かせる技術」を磨く方向に重心を置いて行く感じは、自分自身の実感としても容易に想像できる。
スポーツの競技団体の中で、パワハラが蔓延する理由のひとつは、おそらくここのところにある。
スポーツが競技として行われる現場では、コーチと選手、監督とコーチ、団体の役員と平職員、先輩と後輩といった様々な立場の間に、上下関係というのか「命令と服従」の関係が生じる。というよりも、競技の習得や継続に伴って生じる人間関係は多かれ少なかれ上下関係を含んでいる。これは避けることができない事実でもあれば、仕方のないことでもある。
なんとなれば、競技に関連する技術や、練習方法や戦術を教える立場の人間は、それを習得する立場の選手よりも上の立場に立っている。また、そうでなければ教えるという動作は貫徹され得ないからだ。
そして、コーチングの内容を洗練することよりも子供たちを指示通りに動かすことに熱中するタイプの指導者は、やがて選手を恐怖によってコントロールするようになる。
直接に手を出すことをしなくても、たとえば怒鳴りつけるとか、罰走を命じるとか、レギュラーから外すとか、恫喝の仕方はいくらでもある。
しかも、現場レベルでは、この種の恫喝は、少なくとも短期的には一定の効果を発揮する。
だからやめられない。
いつだったか、ラグビーの日本代表チームの監督をつとめたエディー・ジョーンズ氏が、何かのインタビューの中で、
「日本のスポーツ指導者には、選手を服従させることを自己目的化してしまっているケースが目立つ」
という意味のことを言っていたことを思い出す。
選手に服従を求めるのは、あくまでも戦術を徹底するためであったり、練習への真剣な取り組みを求めるための手段であって、服従そのものが目的ではない。
従って、練習時間が終わった時や、グラウンドの外でまで服従を求めるのは本来筋違いだ。
服従は、競技内のあるいは競技時間内の設定に過ぎない。
が、日本の指導者は、1年365日、1日24時間の服従を求める。
そうなると選手の中に自主性と責任感が育たなくなる。そこが問題だ。
と、おおよそそんな話をしていたはずだ。
ほとんど同じ内容をかつてサッカーの日本代表を率いたハンス・オフト氏が指摘している。
彼は、日本人選手の長所は「コーチャブル」であることだが、欠点もまた「コーチャブル」であるところにあるというお話をしていた。
彼の言うには、代表選手になるような一流のプレイヤーは、海外では、容易に他人の話を鵜呑みにしない。こちらが戦術を授けたり練習方法を提案しても、簡単には賛同せず、逆に言い返してくるケースすらある。
なので、たとえばオランダのチームで、選手たちを自分のやり方で指導するためには、それなりの議論と試行錯誤と軋轢と対立を覚悟せねばならない。
その点、日本人選手は、一流選手であっても、一瞬でこちらの意図を理解し、言った通りに動いてくれる。そういう意味では非常に教えやすい。
ただ、教えたことをこなしているようでいて、こっちの意図を理解していないケースもあるので、その点は油断がならない、と、そういうお話もしていた。
オフト氏の何代か後に日本代表チームを指揮したフィリップ・トルシエ氏も、よく似た指摘をしている。
彼は、
「時には赤信号を渡らなければいけない」
という、とても彼らしい言い方で、日本人選手に不服従(というよりも、「自分のアタマで考えて判断すること」)を求めた。
話がバラけている。
大切なのは、他人を指導する立場の人間は、スポーツの指導者であれ、競技団体の幹部であれ、企業の管理職や大学の教員であれ、やがて他人の服従に嗜癖するようになるということだ。
ごく幼い時代から教室から排除されないための技術である「服従」を第二の天性として身につけているわれら日本人の場合、リーダーの側の他者コントロールへの嗜癖は、より容易に学習されるはずだ。
リーダーが権力的に振る舞うことを
「役職が人を作る」
という言い方で、積極的に評価する見方もある。
組織の中で責任ある立場を経験した若者が、やがてリーダーとしての自覚と責任を身につけていく、という感じのストーリーを想定しているのだと思う。
もちろんそういう面はある。
すべての人間が生まれつきのリーダーでない以上、多くの管理者や指導者は、経験によって指導者の資質なり能力を獲得すると考えた方が辻褄が合う。
ただ、スポーツのコーチの中に、選手を服従させることを自己目的化してしまう不心得者がいるのと同じように、企業の管理職や政治家の中にも、他人を服従させることそれ自体を目指してしまうパワハラ体質の人間が一定数含まれていることも、また事実だ。
思うに、われわれのこの島国が、こんなにちまちました社会であるにもかかわらず、これほど大量のパワハラ人種を育んでいるのは、結局のところ、わたくしども21世紀の日本人が、つまるところ「支配と服従」以外の人間関係の取り結び方をコーチングされていないからなのではあるまいか。
言い過ぎだったかもしれない。
でも撤回はしない。
この問題は、もうしばらく考えてみることにする。
アメリカ合衆国という国について、ひとつ感心するのは、たとえば、大統領の任期を二期8年までとする原則を、建国以来頑なに守っている(※)ことだ。これは、見事な態度だと思っている(※例外は、第二次大戦中のフランクリン・ルーズベルト大統領)。
国家元首の任期を後になって改めている国は少なくない。はじめから任期を定めていない国もけっこうある。
個人的には、オバマさんにあと4年やってもらっても良かったのではなかろうかと思わないでもないのだが、やはりどんなに立派な人間であっても、必要以上に長く権力の座にとどまるべきではない。
権力の頂点に立っていればいずれその行使に嗜癖するようになる。たとえ本人に権力志向が皆無でも、長期化した権力は、システムの自動運動として自己の永遠化をセルフプログラミングするようになる。
最後に、スポーツの世界からパワハラを駆逐するための私案を提示しておく。
とりあえず「強化」という思い込みを放棄するのがてっとりばやいと思う。
そのために、東京オリンピックでメダルゼロを目指してほしい。
五輪終了時点で、メダルゼロが達成できているのであれば、パワハラはウソみたいに消えているはずだ。その地点から、あらためてメダルを目指す方法についてゼロベースで考えはじめるのが正しい方法だと思う。
それなら、炎暑の東京で開催する意義もすこしはありそうだ。
ぜひ、試してみてほしい。
(文・イラスト/小田嶋 隆)
オダジマさんを服従させる快感に一度酔ってみたいです。
小田嶋さんの新刊が久しぶりに出ています。本連載担当編集者も初耳の、抱腹絶倒かつ壮絶なエピソードが語られていて、嬉しいような、悔しいような。以下、版元ミシマ社さんからの紹介です。

なぜ、オレだけが抜け出せたのか?
30 代でアル中となり、医者に「50で人格崩壊、60で死にますよ」
と宣告された著者が、酒をやめて20年以上が経った今、語る真実。
なぜ人は、何かに依存するのか?
<< 目次>>
告白
一日目 アル中に理由なし
二日目 オレはアル中じゃない
三日目 そして金と人が去った
四日目 酒と創作
五日目 「五〇で人格崩壊、六〇で死ぬ」
六日目 飲まない生活
七日目 アル中予備軍たちへ
八日目 アルコール依存症に代わる新たな脅威
告白を終えて
日本随一のコラムニストが自らの体験を初告白し、
現代の新たな依存「コミュニケーション依存症」に警鐘を鳴らす!
(本の紹介はこちらから)
記事本文中の「大統領の任期を二期8年までとする原則を…」の後に注記を加えました。ご指摘をいただいた皆様、ありがとうございました。[2018/09/14 11:00]
登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。
※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。
この記事はシリーズ「小田嶋隆の「ア・ピース・オブ・警句」 ~世間に転がる意味不明」に収容されています。フォローすると、トップページやマイページで新たな記事の配信が確認できるほか、スマートフォン向けアプリでも記事更新の通知を受け取ることができます。










